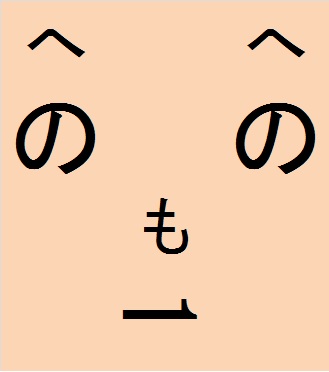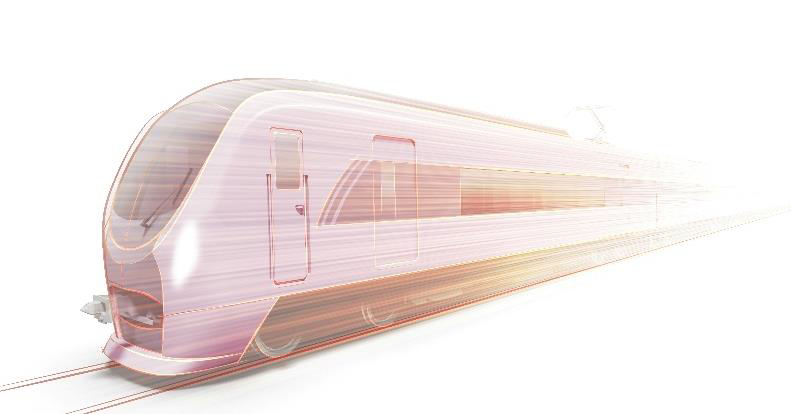
京成電鉄の新型有料特急車両にチューモーク!
2025/6/4
2025年5月21日(水曜日)、京成グループ中期経営計画と京成電鉄のプレスリリースで、2028年度の運行開始を目指し、新型有料特急車両の設計に着手したことを発表した(冒頭の画像は京成電鉄提供〔以下、京成〕)。注目は押上―成田空港間の運転である。さらに、〈スカイライナー〉次世代車両の検討も発表し、新しい時代の到来が近づこうとしている。
京成の特急系列車は2種類

2代目3100形は乗車券のみで利用できるアクセス特急を中心に運用。
「新型有料特急車両」の文言に疑問を持つ読者がいると思われるので、京成の特急系列車について御説明しよう。
現在の特急系列車は、「乗車券のみで乗れる列車」と「ライナー券が必要な列車」の2種類がある。
前者は通勤形電車を使用し、座席は基本ロングシート(注:相互直通運転を行なう鉄道事業者によっては、車端部にボックスシートを備えるセミクロスシート車が存在する)。特急、通勤特急、快速特急、アクセス特急の4種類がある。
後者は特急形電車を使用し、座席はリクライニングシート。ただ、列車種別はすでに特急が使われているため、〈スカイライナー〉〈モーニングライナー〉〈イブニングライナー〉〈シティライナー〉〈臨時ライナー〉は、「列車愛称 兼 列車種別」である。ボクシングに例えると、前者は1位に相当。後者はその上をゆくチャンピオンに相当するので、“チャンピオン列車”と言える。
なお、『京成時刻表』VOL.33(発行は京成、編集・販売はJTBパブリッシング)では、スカイライナー券の料金を「特急料金」、モーニング・イブニングライナー券などの料金を「料金」と称している。ちなみに〈臨時ライナー〉は1・2号車のみ利用可の定員制(料金を払えば空いている席に坐れる)で、車内で発売する特急料金は500円也。
参考までに「列車愛称 兼 列車種別」は、東武鉄道(以下、東武)の〈TJライナー〉〈THライナー〉、西武鉄道の〈S-TRAIN〉〈拝島ライナー〉、京王電鉄の〈京王ライナー〉〈Mt.TAKAO号〉がある。東武の〈TJライナー〉と京王電鉄は特急より上位に対し、それ以外は下位である(詳細は割愛)。
さらに名古屋鉄道2000系ミュースカイは「車両愛称 兼 列車種別」で、“チャンピオン列車”にあたる。
現在の特急系列車は、「乗車券のみで乗れる列車」と「ライナー券が必要な列車」の2種類がある。
前者は通勤形電車を使用し、座席は基本ロングシート(注:相互直通運転を行なう鉄道事業者によっては、車端部にボックスシートを備えるセミクロスシート車が存在する)。特急、通勤特急、快速特急、アクセス特急の4種類がある。
後者は特急形電車を使用し、座席はリクライニングシート。ただ、列車種別はすでに特急が使われているため、〈スカイライナー〉〈モーニングライナー〉〈イブニングライナー〉〈シティライナー〉〈臨時ライナー〉は、「列車愛称 兼 列車種別」である。ボクシングに例えると、前者は1位に相当。後者はその上をゆくチャンピオンに相当するので、“チャンピオン列車”と言える。
なお、『京成時刻表』VOL.33(発行は京成、編集・販売はJTBパブリッシング)では、スカイライナー券の料金を「特急料金」、モーニング・イブニングライナー券などの料金を「料金」と称している。ちなみに〈臨時ライナー〉は1・2号車のみ利用可の定員制(料金を払えば空いている席に坐れる)で、車内で発売する特急料金は500円也。
参考までに「列車愛称 兼 列車種別」は、東武鉄道(以下、東武)の〈TJライナー〉〈THライナー〉、西武鉄道の〈S-TRAIN〉〈拝島ライナー〉、京王電鉄の〈京王ライナー〉〈Mt.TAKAO号〉がある。東武の〈TJライナー〉と京王電鉄は特急より上位に対し、それ以外は下位である(詳細は割愛)。
さらに名古屋鉄道2000系ミュースカイは「車両愛称 兼 列車種別」で、“チャンピオン列車”にあたる。
成田空港発の列車は押上方面行きが多い

成田空港13時48分発の快速(押上から各駅停車)西馬込行きがまもなく押上に到着。
新型有料特急車両、最大の注目点は本線京成上野発着ではなく、押上線押上発着であること。押上は京成最初の路線として、1912年11月3日(日曜日)に開業した由緒ある駅だ。当時は地上に所在していた。
意外と思われるかもしれないが、日中時間帯の成田空港発は〈スカイライナー〉を除き、押上方面行きの列車にそろえている。代表的なのは成田空港線経由のアクセス特急で、成田空港―押上間を55分で結ぶ。惜しむらくは40分間隔を基本としていることで、〈スカイライナー〉の補完列車のような役割を担う。また、大半の列車は押上から列車種別をエアポート快特に変え、都営浅草線(東京都交通局)経由で京浜急行電鉄の羽田空港国内線ターミナルに向かう。
本線経由の快速(都営浅草線内は各駅停車)は京成津田沼まで各駅に停まるため、押上まで約1時間20分を要する。列車によっては、途中の京成成田で始発の快速特急京成上野行き、青砥でアクセス特急(押上からエアポート快特)羽田空港国内線ターミナル行きに乗り継ぐことで約1時間10分に短縮される。運賃は本線経由が安いとはいえ、時間がかかるほか、大きな荷物を抱えての乗り換えが面倒で、坐れる保証もない。
現在、新鎌ヶ谷・青砥停車の〈スカイライナー〉に乗り、青砥でアクセス特急に乗り換えた場合、成田空港―押上間の所要時間は47分である。新型有料特急車両による列車の所要時間について、新鎌ヶ谷・青砥停車の場合は上記とほぼ同じ、通過の場合は若干短縮すると思う。
ただ、新型有料特急車両の押上―成田空港間の経路について、京成は「詳細については順次検討していく」という。本線経由だと京成船橋や京成津田沼に停車する可能性もあるだろう。成田空港線経由は〈スカイライナー〉と同じ160km/h運転の可能性もある。
意外と思われるかもしれないが、日中時間帯の成田空港発は〈スカイライナー〉を除き、押上方面行きの列車にそろえている。代表的なのは成田空港線経由のアクセス特急で、成田空港―押上間を55分で結ぶ。惜しむらくは40分間隔を基本としていることで、〈スカイライナー〉の補完列車のような役割を担う。また、大半の列車は押上から列車種別をエアポート快特に変え、都営浅草線(東京都交通局)経由で京浜急行電鉄の羽田空港国内線ターミナルに向かう。
本線経由の快速(都営浅草線内は各駅停車)は京成津田沼まで各駅に停まるため、押上まで約1時間20分を要する。列車によっては、途中の京成成田で始発の快速特急京成上野行き、青砥でアクセス特急(押上からエアポート快特)羽田空港国内線ターミナル行きに乗り継ぐことで約1時間10分に短縮される。運賃は本線経由が安いとはいえ、時間がかかるほか、大きな荷物を抱えての乗り換えが面倒で、坐れる保証もない。
現在、新鎌ヶ谷・青砥停車の〈スカイライナー〉に乗り、青砥でアクセス特急に乗り換えた場合、成田空港―押上間の所要時間は47分である。新型有料特急車両による列車の所要時間について、新鎌ヶ谷・青砥停車の場合は上記とほぼ同じ、通過の場合は若干短縮すると思う。
ただ、新型有料特急車両の押上―成田空港間の経路について、京成は「詳細については順次検討していく」という。本線経由だと京成船橋や京成津田沼に停車する可能性もあるだろう。成田空港線経由は〈スカイライナー〉と同じ160km/h運転の可能性もある。
押上発着のメリット

左は東武の特急〈スペーシア X〉、右は京成バスの墨田区内循環バス。
押上は東京メトロ半蔵門線、東武伊勢崎線(押上と後述のとうきょうスカイツリーは同一駅扱い)の乗り換え駅、東京スカイツリータウン下車駅も相まって、2023年度の乗降者数は20万9421人という、京成きってのマンモス駅である。朝ラッシュ時の上り京成曳舟―押上間の混雑率も149%で、こちらも京成きってのドル箱路線でもある。
加えて、押上線と都営浅草線の境界駅(京成管理駅)なので、ダイヤは相互直通運転がメイン。下り青砥方面の始発列車は平日10本、土休5本(すべて各駅停車)と格段に少ない。新型有料特急車両を導入することで、“必ず坐れる列車”が増える。
京成にとっての押上は、グループが運行する路線バス、運営するホテルがあること。エリアの価値向上、各事業へのシナジー効果(共力作用による相乗効果)が期待できると見ている。また、私の見方として、東武エリアながら、東京スカイツリータウンへの観光客も呼び込める。特に成田国際空港着の航空機で来日した外国人観光客を誘致しやすい。全車指定席の有料特急を設定すれば、より快適に移動できる。
さらに押上駅から徒歩約6分の伊勢崎線とうきょうスカイツリー駅(現在、下りホームと上りホームは、改札口の場所が異なる)は、東武特急が全列車停車するので、日光・鬼怒川・館林方面への観光客誘致も期待できる。成田空港―押上―とうきょうスカイツリー―日光・鬼怒川・館林方面といった有料特急回遊ルートを構築することになり、外国人観光客にとっては、より日本を満喫できるだろう。
なお、京成に確認したところ、新型有料特急車両は都営浅草線、京浜急行電鉄への直通運転がない模様。2代目AE形も引き続き京成上野発着の列車として運行する。
加えて、押上線と都営浅草線の境界駅(京成管理駅)なので、ダイヤは相互直通運転がメイン。下り青砥方面の始発列車は平日10本、土休5本(すべて各駅停車)と格段に少ない。新型有料特急車両を導入することで、“必ず坐れる列車”が増える。
京成にとっての押上は、グループが運行する路線バス、運営するホテルがあること。エリアの価値向上、各事業へのシナジー効果(共力作用による相乗効果)が期待できると見ている。また、私の見方として、東武エリアながら、東京スカイツリータウンへの観光客も呼び込める。特に成田国際空港着の航空機で来日した外国人観光客を誘致しやすい。全車指定席の有料特急を設定すれば、より快適に移動できる。
さらに押上駅から徒歩約6分の伊勢崎線とうきょうスカイツリー駅(現在、下りホームと上りホームは、改札口の場所が異なる)は、東武特急が全列車停車するので、日光・鬼怒川・館林方面への観光客誘致も期待できる。成田空港―押上―とうきょうスカイツリー―日光・鬼怒川・館林方面といった有料特急回遊ルートを構築することになり、外国人観光客にとっては、より日本を満喫できるだろう。
なお、京成に確認したところ、新型有料特急車両は都営浅草線、京浜急行電鉄への直通運転がない模様。2代目AE形も引き続き京成上野発着の列車として運行する。
成田空港へのアクセス強化

2代目AE形は9編成72両在籍。
成田国際空港は機能強化の一環として、新しい滑走路や旅客ターミナルの整備を進めている。2024年の訪日外国人は3687万人で、政府は2030年に6000万人の目標を掲げている。京成も宗吾車両基地の拡充工事を進め、2029年3月の完成を目指す。
京成の看板列車、〈スカイライナー〉利用客の2014年度は約330万人で、10年たった2024年度は約840万人に増加。2020・2021年度はコロナ禍の影響で急落したが、2022年度以降、右肩上がりが続いている。さらに現在は一部列車を青砥と新鎌ヶ谷に停車し、新たな需要の開拓に努めた。例えば、京成上野―新鎌ヶ谷間を“通勤ライナー感覚”で乗車した方もいるだろう。
現在、鉄道による日中時間帯の成田空港アクセスを見ると、〈スカイライナー〉は20分間隔、成田空港線のアクセス特急は40分間隔、本線の快速は約20分間隔で、JR東日本成田線の成田空港支線(日中時間帯の特急〈成田エクスプレス〉は毎時2本、快速と各駅停車は毎時1~2本)に比べ、格段に多い。新型有料特急車両が押上―成田空港間の運転に加わると、京成の利便性がさらに増す。
京成の看板列車、〈スカイライナー〉利用客の2014年度は約330万人で、10年たった2024年度は約840万人に増加。2020・2021年度はコロナ禍の影響で急落したが、2022年度以降、右肩上がりが続いている。さらに現在は一部列車を青砥と新鎌ヶ谷に停車し、新たな需要の開拓に努めた。例えば、京成上野―新鎌ヶ谷間を“通勤ライナー感覚”で乗車した方もいるだろう。
現在、鉄道による日中時間帯の成田空港アクセスを見ると、〈スカイライナー〉は20分間隔、成田空港線のアクセス特急は40分間隔、本線の快速は約20分間隔で、JR東日本成田線の成田空港支線(日中時間帯の特急〈成田エクスプレス〉は毎時2本、快速と各駅停車は毎時1~2本)に比べ、格段に多い。新型有料特急車両が押上―成田空港間の運転に加わると、京成の利便性がさらに増す。
〈スカイライナー〉第4世代車両の検討

歴代の〈スカイライナー〉車両(左はAE100形、右は初代AE形)。
今回の京成グループ中期経営計画で、もうひとつの注目は「次期スカイライナー車両の検討」である。成田空港輸送需要の右肩上がりが続いており、対応策として検討していくそうだ。さらに現行の8両編成から長編成化(9両編成もしくは10両編成のいずれかと思われる)を視野に入れているという。
私が知る限り、京成上野、日暮里(高架ホームのみ)、青砥、東成田(旧成田空港駅)のホームは10両分の長さを確保している。京成に確認したところ、「ホーム有効長の定義は『当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車から、最も後方にある旅客車までの長さのうち、最長のものの長さ以上』となり、現在10両が止まれる駅はございません」の由(よし)。京成上野はホームの柵が2両分設置されたほか、日暮里のホームドアは8両分設置されたので、10両編成の列車が停車できない。
ホーム有効長についての定義は、各鉄道事業者に一任のようである。例えば、近畿日本鉄道けいはんな線のホームは8両分の長さだが、ワンマン運転開始によるホームセンサーの設置により、ホーム有効長は6両分に短縮された。
さて、〈スカイライナー〉の第1世代車両は初代AE形で、1972年に登場し、1993年に引退。第2世代車両はAE100形で、1990年に登場し、2016年に引退。第3世代車両は2代目AE形で、2009年に登場した。いずれの車両も“フラッグシップ”として、一時代を築いたのは言うまでもない。
関東地方の大手私鉄で10両編成以上の列車がないのは、京成のみ。〈スカイライナー〉の第4世代車両は京成初の10両編成に期待したい。さらなる輸送力増強が図れるので、ライナー券がより買いやすくなる。仮に9両編成で登場した場合、私鉄、地下鉄に限定すると、大阪市営地下鉄(現・Osaka Metro)御堂筋線及び、相互直通運転を行なう北大阪急行電鉄(いずれも1987年から1996年まで)以来となり、趣味的な視点では“レア”な存在となる。
私が知る限り、京成上野、日暮里(高架ホームのみ)、青砥、東成田(旧成田空港駅)のホームは10両分の長さを確保している。京成に確認したところ、「ホーム有効長の定義は『当該プラットホームに発着する列車の最も前方にある旅客車から、最も後方にある旅客車までの長さのうち、最長のものの長さ以上』となり、現在10両が止まれる駅はございません」の由(よし)。京成上野はホームの柵が2両分設置されたほか、日暮里のホームドアは8両分設置されたので、10両編成の列車が停車できない。
ホーム有効長についての定義は、各鉄道事業者に一任のようである。例えば、近畿日本鉄道けいはんな線のホームは8両分の長さだが、ワンマン運転開始によるホームセンサーの設置により、ホーム有効長は6両分に短縮された。
さて、〈スカイライナー〉の第1世代車両は初代AE形で、1972年に登場し、1993年に引退。第2世代車両はAE100形で、1990年に登場し、2016年に引退。第3世代車両は2代目AE形で、2009年に登場した。いずれの車両も“フラッグシップ”として、一時代を築いたのは言うまでもない。
関東地方の大手私鉄で10両編成以上の列車がないのは、京成のみ。〈スカイライナー〉の第4世代車両は京成初の10両編成に期待したい。さらなる輸送力増強が図れるので、ライナー券がより買いやすくなる。仮に9両編成で登場した場合、私鉄、地下鉄に限定すると、大阪市営地下鉄(現・Osaka Metro)御堂筋線及び、相互直通運転を行なう北大阪急行電鉄(いずれも1987年から1996年まで)以来となり、趣味的な視点では“レア”な存在となる。
課題
2つの新型有料特急車両の期待が大きい半面、課題も山積している。
まず、成田空港線成田湯川―成田空港間が単線であること。途中に信号場、空港第2ビルに交換設備を設けたとはいえ、列車行き違いによるタイムロスが生じる。京成は標準軌(1435ミリ)、JR東日本の大半の在来線は狭軌(1067ミリ)と異なるため、線路の共用ができない。
次に空港第2ビル、成田空港の長大ホームは本線用と成田空港線用に分かれた縦列構造のため、運行の制約が生じること。京成は折り返し機能の改善を図りたいとしている。それ以外の区間でも、線路容量、線形など、施設上の課題があるという。
ただ、成田空港線自体、北総鉄道(京成高砂―小室間、第1種鉄道事業者)、千葉ニュータウン鉄道(小室―印旛日本医大間、第3種鉄道事業者)、成田高速鉄道アクセス(印旛日本医大―成田市土屋間、第3種鉄道事業者)、成田高速鉄道(成田市土屋―成田空港間、第3種鉄道事業者)の線路を借り、列車を運行する(京成は第2種鉄道事業者)。成田湯川―成田空港間の複線化も含め、輸送力増強を図るには“地主”の理解が必要不可欠である。
これからの課題が解決するのは、2030年以降になるものと思われる。
※第1~3種鉄道事業者は文末の用語解説を参照。
まず、成田空港線成田湯川―成田空港間が単線であること。途中に信号場、空港第2ビルに交換設備を設けたとはいえ、列車行き違いによるタイムロスが生じる。京成は標準軌(1435ミリ)、JR東日本の大半の在来線は狭軌(1067ミリ)と異なるため、線路の共用ができない。
次に空港第2ビル、成田空港の長大ホームは本線用と成田空港線用に分かれた縦列構造のため、運行の制約が生じること。京成は折り返し機能の改善を図りたいとしている。それ以外の区間でも、線路容量、線形など、施設上の課題があるという。
ただ、成田空港線自体、北総鉄道(京成高砂―小室間、第1種鉄道事業者)、千葉ニュータウン鉄道(小室―印旛日本医大間、第3種鉄道事業者)、成田高速鉄道アクセス(印旛日本医大―成田市土屋間、第3種鉄道事業者)、成田高速鉄道(成田市土屋―成田空港間、第3種鉄道事業者)の線路を借り、列車を運行する(京成は第2種鉄道事業者)。成田湯川―成田空港間の複線化も含め、輸送力増強を図るには“地主”の理解が必要不可欠である。
これからの課題が解決するのは、2030年以降になるものと思われる。
※第1~3種鉄道事業者は文末の用語解説を参照。
用語解説
第1種鉄道事業者:自社が鉄道線路を敷設し、運送を行なうとともに、線路容量に余裕がある場合に限り、第2種鉄道事業者に使用させることができる。
第2種鉄道事業者:第1種もしくは、第3種の鉄道事業者が敷設した線路を使用して運送を行なう。
第3種鉄道事業者:鉄道線路敷設後、第1種鉄道事業者に譲渡、もしくは第2種鉄道事業者に使用させる事業で、自社は運送を行なわない。
【取材協力:京成電鉄】
第2種鉄道事業者:第1種もしくは、第3種の鉄道事業者が敷設した線路を使用して運送を行なう。
第3種鉄道事業者:鉄道線路敷設後、第1種鉄道事業者に譲渡、もしくは第2種鉄道事業者に使用させる事業で、自社は運送を行なわない。
【取材協力:京成電鉄】
2代目AE形に関する動画。
2代目3100形に関する動画。
岸田法眼の鉄道チャンネル
『Yahoo! セカンドライフ』(ヤフー刊)の選抜サポーターに抜擢され、2007年にライターデビュー。以降はフリーのレイルウェイ・ライターとして鉄...
プロフィールや他の投稿を見る